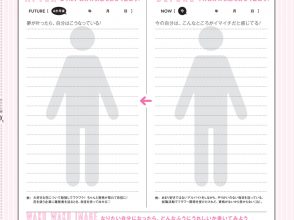カリスマ読者モデルからCanCam専属モデルへ Vol.25押切もえ
CanCam創刊40周年を記念して、歴代のOGモデルをクローズアップするスペシャル連載。専属モデル時代から今日までの軌跡を振り返りつつ、今だから話せる撮影裏話やプライベートなお話など、自分らしく輝き続ける彼女たちのリアルなメッセージをお届けします。
スぺシャル連載のラストを飾るのは、唯一無二の存在感で絶大な人気を誇り、“CanCam”黄金時代の立役者でもある押切もえさんが登場!
高校生の頃からモデルとしてカリスマ的な人気を博した押切もえさん。そんな押切さんが『CanCam』の専属モデルに抜擢されたのは2001年のこと。抜群のスタイルと持ち前のガッツで頭角を現し、“カワイイ”最前線だった『CanCam』の中でも、きれいめからカジュアルまで幅広いファッションを着こなすスターモデルに。山田 優、蛯原友里とともに、『CanCam』黄金期を支え、その人気ぶりは社会現象にもなりました。
カリスマ読モからトップモデルへ、まさに順風満帆に見えたキャリアですが、その裏には努力を止めない真面目でストイックな彼女の姿が…。スタッフやモデル仲間から、常に“頼られる存在”だったという押切さんに、『CanCam』専属モデルの時代を振り返っていただきました。『CanCam.jp』だからこそ語れる、深掘りエピソードをお届けします。
アットホームな現場でも妥協だけはしなかった
ーー『CanCam』の初撮影は覚えていますか?
「はい、前日は緊張のあまりほとんど眠れず、寝不足でスタジオ入りしたのを覚えています。当日は編集スタッフをはじめ、皆さんが本当に優しく迎えてくださって、その時少しホッとしました。メイクルームの中に、憧れていたブランドの服や靴がたくさん並べてあって、それを見ているだけでも本当に幸せで。試し撮りのポラロイド写真を絵コンテに貼りながら、誌面のイメージが見えてくる工程に感動したり、スニーカーの特集で足元がよく見えるポージングを考えてスタッフの皆さんに相談したり、現場でのひとつひとつが本当に楽しかった思い出です」
ーー当時の『CanCam』の撮影現場はどんな雰囲気でしたか?
「緊張感はありつつも、ものすごくアットホーム。編集部のみんなも、スタイリストさんも、モデルたちも、みんなが優しくて温かい人ばかりでとても仲が良かったんです。でも、ただ優しくて仲良しなだけじゃなく、『みんなで考えて妥協しないで、いいものを作ろう!』っていう気持ちが強かったので、それぞれのプロの顔も知っています。意見を伝えたり、アイデアを出し合ったり、お互いに信頼しているからこそできる、プロフェッショナルな現場でした。みんなのアイデアが出尽くしてしまったときに、私が読者モデル時代の経験を活かして『こんな見せ方はどうですか?』って提案したことがあるのですが、『面白い、やってみよう!』と言ってくれて、それも嬉しかったですね」
当時の編集部メンバーは「『CanCam』があれだけ愛される雑誌になれたのは、もえちゃんのプロ意識の高さがあったからこそ」と、口を揃える。早朝から夜まで、1日に何本もの企画を掛け持ちしても、常に全力でカメラ前に立っていた押切さん。ときには、コーディネートの数が100近くなり、現場でミスが起こることも…。それでも疲れた顔を見せず「もう一回着て撮り直せばいいよ!」と、モチベーションを維持し続けていたモデル魂。後輩モデルだけでなく、新人スタッフにも、“仕事はこうやってするものだ”というプロの姿を、存在そのもので教えてくれた。
ーー社会現象にもなった『CanCam』ブーム、どう感じていましたか?
「“うれしい”のひと言! 私が『CanCam』に入ったばかりの頃は、他に競合誌がたくさんあって、みんなで心をひとつにして必死に頑張っていたので。読んで欲しい、という気持ちが多くの方に伝わっているのを知るたびに、やりがいを感じていました。誌面で紹介した小物や着用した服を街中で見かけるようにもなって、それも嬉しかったですね」
ーーいちばん印象に残っている撮影は?
「やっぱり…単独での初表紙かな。とても嬉しかったですし、このポージングも自分らしさが出せていたんじゃないかなって思います。他には、朝4時起きで、いろいろな企画を3〜4本撮影した日のことが今でも忘れられないですね。まぁ、ここまでは通常ですが…(笑)。最後の撮影を終えたところで、写真を確認していたライターさんが、『なんか、バック紙(スタジオの背景カラーのこと)の色がイメージと違う気がする』と悩みはじめて、撮影後に写真を撮り直すことになったんです。バック紙とライトを変えるのに時間がかかるのでひとまず待機して、そこから衣装も着直して、しかも深夜2、3時の地下スタジオで…(笑)。私は、いいモノを作るために愚痴は絶対に言わないって決めていたので、『やりましょう!』と言ったのですが、そのときは疲れていたんでしょうね、気持ちと体力が噛み合わなくて、メイクルームで涙がポロリと一粒流れて…、メイクさんに『ごめんね、今日だけは許して』と言って、笑いながらごまかしたのを覚えています」

撮影の思い出を語る中で、やはり見え隠れするのは押切さんの高いプロ意識。当時の『CanCam』は、誌面が500ページ以上になることもしばしば。企画も多く、スタッフやモデルが担当する撮影のボリュームは想像を超えていました。そんなときでも、 “絶対に愚痴は言わない”と決めていた、その強い気持ちは一体どこからきていたのか。
「私もちょっとはネガティブな言葉を言ってしまったこともあると思います。でも、できるだけ言わないようにしていて、というのも文句を言った時点で自分の気持ちも折れちゃうし、それを受け取った人も同じ気持ちになってしまうと思うから。“イヤだよね”っていうムードが私は好きではないし、文句や愚痴を言っても何もプラスに変わらない。その前に、一生懸命やっちゃったほうがいいでしょ?っていうタイプなんです。でも、最初からそういうタイプだったわけではないのかも。私は、『CanCam』の専属モデルになる前にお仕事がない時期を経験しているので、仕事のありがたみを常に感じていたし、もしお仕事がたくさんいただけるようになったらこうしたい!とか、絶対に投げ出さないで結果を出そう、と思っていたからだと思います」
大変だったからこそ、チーム感も強かった!
ーーヒヤッとするような撮影エピソードはありますか?
「まだ専属モデルになりたての頃だったと思うのですが、一度だけ寝坊をしたことがあって、目が覚めた瞬間の『あ、終わった…』という気持ちが今も忘れられないです(笑)。集合時間に電話がかかってきたんです、しかも実家に! 携帯の充電が切れていたみたいで、アラームも鳴らなくて。私は東京に住んでいなかったので、どんなに急いでも1時間はかかってしまうし…焦りながら向かいました。それ以来、寝る前は携帯の充電をちゃんとチェックして、目覚ましをかけるようになりました。
あと、その反対で、スタッフが来なかった…というエピソードもありました(笑)。確か、“〇〇vs〇〇 1か月の着回し”企画だったと思うんですが、同時進行でほかの企画も一緒に撮影していたんです。優ちゃんと友里ちゃんと朝は一緒だけど、それぞれ途中で他の企画の撮影を挟んで、また夜に合流して一緒に撮影をするとか、とてもハードなスケジュールが数日続いていたんです。そんなある日、現場に入ると私とメイクさんしか集合時間に集まっていない、ということがありました。ライターさんに電話をしても繋がらないし、他のスタッフもみんな寝坊。とにかくハードな週だったので、体力の限界だったのだと思います。スタイリストさんがコーディネートルームに泊まっていたり、ライターさんが撮影準備で徹夜をしたり…読者の方が喜んでくれる誌面を作るためにみんなが頑張っていて。だからこそ、CanCamはチーム感も強かった」
ーー超多忙な日々、どうやってモチベーションを維持しましたか?
「モチベーションが落ちそうになったときは、当時はスマホもなかったですし、先人の知恵を借りようと思って、読書と映画鑑賞で息抜きをしていました。私は『CanCam』の専属モデルになったのが他の方よりもちょっと遅くて、年上のほうだったんです。しかも専属になったときに、先輩モデルの方々の卒業が続いて、悩みを相談できる方もなかなかいなくて。なので、年下ですが(山田)優ちゃんにはいろんな話を聞いてもらっていましたね。CanCamの中での方向性のすり合わせや現場の雰囲気づくりについては、よく編集スタッフの方とも話をしたり。あとは、ダンスを10年ほど習っていたので、それもリフレッシュになっていたと思います」
超多忙のスケジュールでも、ネガティブな言葉で発散することより、プロとして最善を尽くすことにこだわりを持ち続けていた押切さん。CanCamの読者はもちろん、優しさと芯の強さを持っている押切さんは、他のモデルやスタッフを常に引っ張る存在でした♡
★次回は、社会現象にもなった『CanCam』ブームの渦中で、当時どんなふうに過ごしていたのか…専属モデル時代をさらに深掘りしていきます!