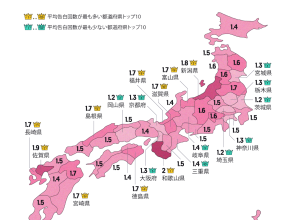よく「気分屋なのが嫌だ」「部下の話を聞かない」、なんて挙げられることが多い「面倒な上司」の特徴。「あるある~」と思いながら見ている方も多いではないでしょうか。でもちょっと待って、もしかしたら部下側も上司から見れば「こんな部下は面倒!」と思われていることがあるかも……。
そこで、株式会社ネクストレベルが部下を持った経験がある上司世代男女166人を対象に行なった、「困った部下」に関するアンケートの結果を紹介します!
■「困った部下を持ったことがある」に100%が「YES」
仕事ができない・扱いにくいなどの「困った部下」を持った経験があるか尋ねたところ、なんと回答いただいた166人全員が困った部下を持った経験が「ある」と回答。みなさん上司ならではの苦労がある様子です。では、いったいどのような部下に困らされたことが多いのでしょうか。
■こんなタイプに手を焼いた!上司166人が答えた「困った部下ランキング」
経験豊かな上司のみなさんでも手を焼く「困った部下」の数々。トップ10は以下の通り。
第1位は、およそ3人に1人が回答した「責任感がない」でした。次いで、2位に「やる気・意欲がない」「指示待ち・受動的」、4位に「報連相がない」、5位に「勝手に判断してしまう」「話が通じない」が続きます。では実際に寄せられたコメントとともに、ランキングを詳しく見てみましょう。
第5位:勝手に判断してしまう(28.9%)
- 指示した内容とは違う業務を自己判断で行ってトラブルになった。本人は気を利かして会社のためにやったと思っている…。
- 仕事のやり方はきちんとマニュアル化されていたのに、自己判断で勝手な行動をした人がいた。ミスに気づくのが遅くなりこちらの残業が増えた。
「自ら動く」ということができているのは良い点ではありますが、その場面によっては困ってしまいます。特に会社でのやり方が決まっているものに関しては、一度確認してほしいですよね。
第5位:話が通じない
- 極力やさしく、相手に伝わるように言ったつもりでも、なかなか伝わらずこちらも疲弊した。
- 話が伝わらず、こちらが伝えたことを本人の思った形で解釈する。わかっていないのに「わかった」と言うが、結果頼んだことができていない。
とりあえずの「わかりました」という返事。そう言われたからには任せるしかありませんが、ギリギリになって「実はわかっていなかった」なんて判明した時、取り返しがつかない状況になってしまってはたまったものじゃありません。わからないことや解釈に不安がある時は、伝えてもらえた方が上司側も状況を把握できます。
第4位:報連相がない
- 報連相がなく、依頼した仕事が終わっているのか遅れているのかなど、状況がわからず困りました。
- 保育関係の仕事ですが、報連相なしに自己判断で子どもへの対応を決めて、保護者へ報告までしてしまった。
新入社員など、特に慣れないうちは「報・連・相」! 一人で行う仕事ではないからこそ、進捗や変更点、突発的なトラブルこそ共有しましょう。仕事が効率的になったり、ミスや問題の早期発見にもつながります。
第2位:指示待ち・受動的
- こちらから作業を振らないと何も行動しない。自分で考えて行動しない。
- 仕事の目的やゴールを説明し、進め方の要点を説明するのだが、言われた作業しかせずに「次は何をやりますか?」と聞いてくる。まるで自分で考えていない。
始めのうちは指示を受けなければ動けない場面も多いですが、慣れてくればきっと今何ができるのか見えてくるはず。自信がない時は「○○を考えているのですが、どうでしょうか」みたいに、考えへの確認を行うところから始めると、どこまで自己判断でできることなのか掴んでいけるのではないでしょうか。
第2位:やる気・意欲がない
- 何か指摘をしても「はぁ」「あぁ…」という生返事しか返って来ない。
- 「失恋をしたのでやる気がでません」と言い出して、会社にはいるのですが何もしない。「辛かったら早退してもいいよ」と声をかけましたが、「帰ると考えちゃうから」と帰社時間までいました。途中泣いたり机を叩いたりして本当に迷惑でした。
プライベートで落ち込むことがあったり、やる気がでない状況は否定できませんが、だからといってあからさまな態度に出ていると周囲の人も正直モヤモヤ。最低限、返事はしっかりとして欲しいところ。自分でも気分を切り替えられる工夫を用意しておきましょう。
第1位:責任感がない
- 指示をしても「わからない」という理由で、他の従業員に仕事を回そうする。仕事に対する責任感がない。
- 責任感が乏しく、期限ぎりぎりになって「できない」と泣きついてきます。結局みんなで徹夜して資料を作成。
- 最も衝撃的だったのは、私が仕事の説明をしている途中でいきなり立ち上がって昼食に出かけたこと。
- 急に連絡が取れなくなり、そのまま休職。引き継ぎなど何もなく、他の部下に仕事を押し付けることとなった。
仕事を受けるからには、大事にして欲しい責任感。できないにしても、「厳しいかもしれない」と感じた時にすぐ共有してほしいところ。ここでも「報連相」の重要さが垣間見えますね。
その他
ランクインはしなかったものの、ほかにもインパクトがある部下とのエピソードが多数あったのでいくつかご紹介します。
- 電話が鳴ったので「○○さん、ちょっと出てください」とお願いしたら「私、電話苦手なんで」と断られた。
- 「次は気を付けて」と注意をしたが、すぐ後に鼻歌を歌いながら仕事していた。反省の色がない。
- 研修中に先輩の作業を見て覚えるようにと言ったところ、「やっている人間のスキルが低くて参考にならない」と返された。
- 「消費税ってなんですか?」と質問されたので、そこから説明しなきゃいけないのか…とがっくりしました。
- 注意したらトイレに隠れてしまった。親が会社に来てトイレからやっと出てきた。親を呼んだのは部下本人。親に「もう辞める」と駄々をこねて辞めていった…。
部下には部下の言い分があるとは思いますが、とはいえ上司の皆さんもお疲れさまです…。
■どう接している?困った部下への対処法
困った部下を野放しにしておくわけにもいかないのが上司の辛いところ。そこで166人の上司の皆さんに、困った部下への対処法を聞いてみました。その中で、最も多かったのが「やんわり指摘する」で68.1%でした。今の時代、たとえ上司の側に悪気がなくても、注意や指摘は対応や言い方を間違えてしまうと「ハラスメント」に思われてしまいます。そのため、威圧的にならないように「やんわり」が今どきの部下への対処法のようです。
- 問題点はやんわり指摘して、原因と再発防止策を自分で考えてもらうようにする。
- まず前提として、褒めたり感謝するところから話し始めます。でないと聞く耳も持っていただけませんので。その上でなにがどう問題だったのかを伝えて納得していただきます。
- まともに指摘すると反発するので、やんわりと指摘して指導。
- 優しく注意したら流されたが、少し口調を強くすると「こわーい」と言われるので、言うのをやめてその人の作業をすべて私がチェックしていた。
- やんわり伝えるようにしていますが、鈍感なようで、はっきり言わないとわからないかも。
パワハラと取られそうになったりと上司の方も苦労が絶えないようです。また、困った部下への対処法2位には「なるべくコミュニケーションをとる・雑談で話しかける」ランクインしました。
- 日頃からコミュニケーションを取って、関係をこじらせないようにしています。
- コミュニケーションを取りつつ、物が言いやすい関係を築くよう心掛けてます。
仕事以外の雑談を話しかけることで、少しずつ信頼関係を築いていくのがポイント。部下からすると上司に話かけるのって結構勇気がいることだったりします。普段の生活に関する話もできるほどの距離間を持てると、仕事の際も話しかけやすいですよね。
そして、2位と似ていますが3位には「話を聞く・ヒアリングする」がランクイン。
- なぜそうなってしまうのかをヒアリングし、こちらが何ができるか、何をしてほしいかを一つずつ確認していく。
- まず本人がどう思っているのか話を聞いた上で、間違っている点を指摘するようにしている。
こちらは雑談ではなく、仕事の話やミス・失敗について本人の意見を聞く事がメインのようです。上司の皆さんもあの手この手を駆使して、なんとか仕事が円滑に進み、本人もやる気が出るようにと考えてくれていました。
■まずはコレから!「仕事のコツ」教えます
今回アンケートにお答えいただいた166人の上司の皆さんも、かつては新人さんだったはず。そこでいま仕事に悩む若手の皆さんに「仕事ができるようになるコツ」を教えてもらい、どんな仕事にも当てはまりやすく、真似しやすいものを厳選。取り入れやすいものから是非試してみて下さいね。
- 必ずメモをとる。
- 言われたことはただやるのではなく、その意味を考えてみる。
- わからないことはとことん聞いてよし。
- 人の話は最後までよく聞きましょう。
- 周りを見る。
- 1日の仕事を始める前に、内容や流れを確認する。
- この人の仕事の仕方いいな、こんな人になりたいなと思う人を見つけて真似る。
- 「自分はできない」と自覚するのは恥ずかしくありません! むしろかわいがられます。
- とにかく笑顔!
■まずはできることから少しずつ
自分よりも長く働く上司と比べると、できないことが多のはあたりまえ。しかし、そのまま「できない~」にしてしまっては、いずれ自分に部下ができるときにも苦労してしまいます。できない、わからないがあるからこそ、確認や報告、人に聞くことなどを後回しにせずに動いていきましょう。(岡美咲)
あわせて読みたい