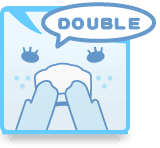一年の中でもとくに春は、気づかないうちに“心と体”ががんばりすぎている時期。新しい職場や引っ越しなど、環境が変化が多く、緊張や不安からストレスが溜まりやすくなります。さらに、ポカポカ陽気が続いたと思えば急に寒くなる…そんな気温差に体が振り回され、自律神経も乱れがちに。
そこで今回は、ストレスと上手に付き合うヒントに加え、管理栄養士・望月理恵子先生にうかがった「ストレスに効果的な栄養素」についてご紹介します。
望⽉理恵⼦(もちづき りえこ)⽒

管理栄養士/山野美容芸術短期大学講師/服部栄養専門学校特別講師/日本臨床栄養協会評議員
サプリメント・ビタミンアドバイザーなど、栄養・美容学の分野で活躍。多くの方が健康情報を学ぶための健康検定協会を主宰するとともに、テレビ・雑誌などで根拠ある栄養学を提供。「栄養学の◯と×」、「やせる時間に食べてみた︕」など著書も多数発刊しており、 現在15冊目の「子どものための時間栄養学(仮)」を執筆中。
Contents
“良いストレス”と“悪いストレス”がある?
「ストレス=悪いもの」と思いがちですが、実はそうとは限りません。ストレスには次の2種類があります。
①良いストレス:行動力・成果を上げるエネルギー源に!
たとえば、新しい目標に向かってチャレンジするときや、プロジェクトやプレゼン、試験などで感じる緊張感。このような⼀時的に感じるストレスは“ユーストレス”と呼ばれ、身体的・精神的なパフォーマンスを向上させることがあるため、良いストレスといわれています。
②悪いストレス:体にも心にも悪影響…
一方で、休む間もないほど忙しかったり、人間関係にずっと悩み続けていたり…「常にプレッシャーを感じる環境」「ゴールの見えない・自分でコントロールできない問題」は“ディストレス”と呼ばれ、心身に大きな負担をかける原因に。無力感や絶望感、不安、集中力の低下といった、メンタルにも体にもさまざまな影響が出やすくなります。
また同じストレス要因であっても、受け止め手の体調や気持ちの状態によって、良いストレス・悪いストレスどちらにもなり得る可能性があります。なので、⾃分が何にストレスを感じやすいのか、どのような状況に耐性を持っているのかを理解することが重要です。
“悪いストレス”をそのまま放置すると、健康やメンタルに悪影響を及ぼすことも…。次に、ストレスに負けないための4つの基本的な対策方法をご紹介します。
ストレスと上手くつきあう基本ポイント4つ
対策① 自分のストレス状態に早く気づく
私たちの日常には、仕事、人間関係、環境の変化など、さまざまな“ストレッサー(ストレスの原因)”が存在します。でも、実際には「自分がどれくらいストレスを感じているか」に気づいていないことが多いもの。
ストレスが慢性化すると、心身の不調へとつながるおそれがあります。だからこそ、ストレスの兆候を早めに察知&早めに対処することが大切です。
【ストレスを感じているときに現れる主なサイン】
・ 心のサイン:不安、緊張、イライラ、悲しみ、憂うつ感、無力感、無気力 など
・体のサイン:食欲不振、痩せる、不眠、腹痛、頭痛、動悸、血圧上昇 など
・行動のサイン:消極的になる、人との関わりを避ける、飲酒・喫煙の増加、落ち着きがなくなる など
こうしたストレスサインが2週間以上続く場合は、うつ病などの可能性もあるので、早めに専門家に相談しましょう。
対策② 睡眠を見直す
良質な睡眠は、ストレスに負けない体づくりの基本。睡眠不足はそれ自体が“生理的なストレッサー”であり、体のリズムを崩してしまう原因にもなります。
【睡眠の質を高めるポイント】
・毎日同じ時間に寝起きする
・寝室や寝具の環境を整える
・昼間に適度な運動を取り入れる
ぐっすり眠ることができると心身の回復力も高まり、ストレスへの耐性もアップ◎。
対策③ 適度な運動を習慣に
軽い運動は、ストレス解消にとっても効果的。体を動かすことで脳内に「セロトニン」や「エンドルフィン」といった神経伝達物質が分泌され、安心感や気分の高まりが得られます。
また、運動によって自律神経のうち交感神経が活性化されることで、ストレスに対処する準備が整います。交感神経の適度な刺激はストレスホルモン「コルチゾール」の分泌を抑える働きもあります。
※運動のしすぎや過度な緊張状態は逆効果になることも。散歩やストレッチなどから始め、無理のない範囲で継続しましょう。
対策④ 栄養バランスのとれた食事を意識
ストレス時にはエネルギー消費が増えるため、栄養を摂ることが大切。特にビタミンやミネラルが不足したり、甘いものやお酒などの嗜好品を摂り過ぎると、ストレス耐性が低下しがちに。
さらに、現代では「孤食」「早食い」「過食」なども問題視されています。食事の内容だけでなく、誰と、どのように食べるかも、心の健康に影響する大事なポイントです。
ストレスに負けない体づくりには、バランスのとれた食事が欠かせません。中でも、ストレスを感じたときに消耗しやすい栄養素を意識的に補うことがカギ。そこで次に「ストレスに強くなるために摂りたい栄養素」について、管理栄養士の望月先生に教えてもらいました。
ストレスと栄養って、こんなに関係ある!
ストレスを感じると、体の中では“コルチゾール”というホルモンが増え、心と体を守ろうと働いてくれます。しかし、分泌状態が長時間続いていると、血糖値の上昇や免疫力の低下など、健康に影響を及ぼしてしまう可能性も。そんなときに、「ビタミン」や「ミネラル」といった栄養素がホルモンバランスの調整をサポートしてくれます。
また、ストレスが溜まると、気分を安定させる“幸せホルモン”セロトニンの生成や働きにも影響が。セロトニンが不足すると、疲労感や不眠、うつ症状が現れることもあります。セロトニンをつくるためには「トリプトファン」というアミノ酸が必要ですが、これは体内で生成できないので食事から摂るほかありません。
このように、ストレスとうまく付き合うには、栄養の力がとっても大切なんです。
管理栄養士がおすすめする「ストレス対策に摂りたい3大栄養素」
①ビタミンB6
ビタミンB群はストレスと戦う味方! 特に「ビタミンB6」は、心の安定に関わる“神経伝達物質”をつくるために欠かせない栄養素です。
【多く含まれる食材】
お肉(牛・豚・鶏)、レバー、マグロなどの赤身魚、ひまわりの種、ピーナッツ、ニンニクなど
【Point】
ビタミンB6は水に溶けやすく光にも弱いため、冷凍や加工の過程で含有量が減ってしまうことも。できるだけ新鮮な食材から摂るのがおすすめ。
②カルシウム
骨や歯を健康に保つだけでなく、実は“神経の伝達”にも関わっているカルシウム。ストレスでピリピリしがちなとき、興奮状態を抑える働きがあります。
【多く含まれる食材】
牛乳・ヨーグルトなどの乳製品、干しエビ、煮干し、海藻、緑黄色野菜など
【Point】
乳製品を中心に、さまざまな食材からバランスよく摂ることが大切。また、カルシウムの吸収をUPさせる「ビタミンD」と一緒にとるのがコツ。インスタント食品や加工食品、肉類に多く含まれる“リン”は、カルシウムの吸収を妨げることがあるので摂りすぎ注意!
③マグネシウム
マグネシウムは神経の興奮をしずめ、メンタルの安定をサポートします。不足すると疲れやイライラが増すことがあるので要注意!
【多く含まれる食材】
ごま、アーモンド、豆類、大豆製品(納豆・豆腐など)に豊富
【Point】
カルシウムを摂り過ぎるとマグネシウムの排泄が増えてしまうので、適切なバランス(目安はカルシウム:マグネシウム=2:1)を意識して摂ることが望ましいです。
幸せホルモンを生み出す栄養素「トリプトファン」
先ほどの3つの栄養素に加えて、ストレス対策に欠かせないのがトリプトファン。心のバランスを整える“幸せホルモン”セロトニンや、睡眠リズムに関わるメラトニンの材料になる必須アミノ酸です。体内で合成できないため、毎日の食事から摂る必要があります。
【多く含まれる食材】
チーズ、ヨーグルト、レバー、大豆製品(納豆・豆腐など)、ナッツ類
【Point】
ビタミン B6 と⼀緒に摂取することで、トリプトファンの働きがよりサポートされるといわれています。
ストレスとうまく付き合うには、「気づく」「整える」「休む」「補う」といった日々の小さなケアの積み重ねが大切。春の不調を見逃さず、心と体をやさしく守る行動をとってみてくださいね!