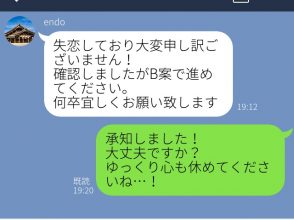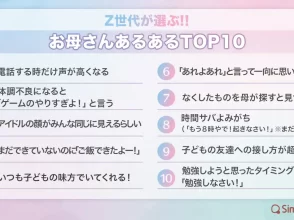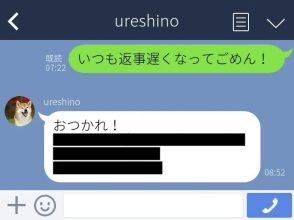部活動の中でも特に大所帯なイメージがある吹奏楽部。人が集まるということはそれだけ個性も集まるということで、吹奏楽部は“あるある”の宝庫なんです。
一説によると、日本の吹奏楽人口は120万人を超えると言われており、吹奏楽部経験者の方や「自分は違ったけど、友達が吹奏楽部だった!」という人はかなり多いのではないでしょうか。
というわけで本日は、元吹奏楽部が思う、現役吹奏楽部の人も元吹奏楽部の人も共感間違いなし!な、楽器パート別の“あるある”木管楽器&コントラバス編をお楽しみください♪
“楽器あるある”木管楽器編
◆フルートあるある
- 「清楚」「優雅」といったイメージを持たれやすい。
実際に本人がそうなのかは置いといて、「清楚」「お嬢様・おぼっちゃま」といった高貴(?)なイメージを持たれることが多いフルート奏者たち。もう一度言うと、本人が実際そうなのかは別なのです。
- ペットボトルやビンを持つと何だか吹きたくなる。
だいたいフルートみたいなもの。
- 優雅なイメージとは裏腹に体育会系な楽器
涼しげに演奏しているように見えても、実際は肩や二の腕、そして何より肺活量が人一倍鍛えられるという体育会系な楽器。澄ました顔の裏は鬼の形相なんです。
- 曲の最後に出番がなくてもかまえて吹いているフリをする
だって寂しいじゃん……
オーボエあるある
- リードの寿命が過ぎてるのに騙し騙し使い続ける
フルート以外の木管楽器に欠かせない“リード”というアイテム。消耗品のため定期的に新しいものを購入するのですが、オーボエとファゴットのリードは1つ約3000円とかわいくないお値段なんです。
中高生のオーボエ奏者は軽い財布を横目に「まだいける、まだいける……」と自分とリードに暗示をかけるのです。
中高生のオーボエ奏者は軽い財布を横目に「まだいける、まだいける……」と自分とリードに暗示をかけるのです。
- 楽器ケースを習字セットに間違われる
クラスのみんな、紛らわしくてごめんね。
- 世界一難しい木管楽器に誇りを持っている
- ていうか正直、木管楽器の中で一番華があると思っている
だって、官能的な音色だし、大事な場面でソロを任されることも多いし、世界一の難易度でギネスにも乗ってるし……ね?
クラリネットあるある
- 吹奏楽部一の大所帯なため、部内の多数決に強い。
クラリネットパートは部活内で一番人数が多いことがほとんど。そのため、クラリネットパートで団結した時の多数決はもはや凶器。なお、パート内のまとまりは……。
- 右手の親指に「クラだこ」ができる。
努力の証。どんどん硬くなり、どんどん戻らなくなる。
- “あの歌”のようになったらと思うとゾッとする。
特に3番!もうそれほとんど音出てないじゃん!
- いいリードにかぎってすぐ割れる
吹きやすいリードにかぎってすぐダメになる現象、アレに名前をつけたい。リードと一緒に木管奏者の心も折れるのです。
サックスあるある
- 首にストラップをつけたまま帰宅
どうして気がつかないのか、楽器を支えるストラップを首につけたまま部室を後にしてしまうのです。ほとんどは部室を出た直前に気づくのですが、稀にそのまま帰宅してしまうことも。
「え、もしかして私、このまま電車乗った……?」
「え、もしかして私、このまま電車乗った……?」
- ポップス曲での異様なソロ率の高さ
他パートの視線が痛い。
- リードの当たり外れが大きい
10枚で約2〜3000円するサックスやクラリネットのリードには当たり外れがあり、自分好みに育てるのです。「育てるってどういうこと」と思うかもしれませんが、やればわかります。育てるんです。クラリネット吹きの筆者はいつも「ソシャゲの10連ガチャかよ」と思いながらリードを育ててます。
- ミスした後や、ソロ吹く前にストラップ調整しがち
特別な効果はないんだけれど、とりあえず気持ちを落ち着かせるためにストラップを調整すること、ありません?
ファゴットあるある
- 口癖は「先生!そこファゴットも吹いてます!」
優しいながらも芯のある音が特徴的なファゴット。オーケストラでは活躍の場面も多いのですが吹奏楽だと指揮者に忘れられることもしばしば……。
先生!忘れないでください!
先生!忘れないでください!
- ファゴット伝わらなさすぎ問題
「こんなに伝わらないことある?」ってくらい未経験者の方に伝わりません。
- ドアを通るとき頭上を気にする
ファゴットは楽器を構えたときや持ったときに、奏者の頭より高い位置に先端がきます。そのため、ファゴット奏者は楽器を持ちながらの移動の時、ぶつけないようにと常に頭上を気にしています。
楽器を持っていなくてもドアを通るときに屈んでしまうことも。
楽器を持っていなくてもドアを通るときに屈んでしまうことも。
コントラバスあるある
- 定期演奏会で楽器回しがち
演奏が波にノってくるとすかさず一回転を挟んできます。さらに、ノッてくると連続で楽器をクルクル回して盛り上げてくれます。
- 分かれて練習する時、複雑
練習中、木管や金管と分かれて練習を行う場面がかなりあります。ですが、コントラバスはどこにも属さないので迷子になりがちです。この記事だって「金管楽器&コントラバス編」って、どこにも属してない感満点です。お願い、誰か拾って。
- 人によって呼び名が違う
コントラバス、弦バス、ストリングベース……統一してくれ!
- 楽器庫に入れると最大の障害物に
とにかくめっちゃスペースを使う。
“楽器別”吹奏楽あるあるはまだまだ前半戦!
今回は、木管楽器とコントラバスのあるあるをご紹介しました。ですが、まだまだこれでは終わりません!次回の吹奏楽部あるある【金管・打楽器編】でお会いしましょう。(くじらおかみおん)